私は個人的に、中公新書から「竹下登」のタイトルの解説書が早く出てくれないかな~と期待しているところがあるのですが、やはりマジメ系の出版社、そして執筆者候補の学者さんは慎重なのでしょうか。なかなか出ません。
そこで取り急ぎChatGPTに解説依頼しました。
竹下登はどういう政治家だったのかな?
竹下登は、いわば「昭和政治の完成形」に近い存在だった。派手な理念やカリスマで引っ張るタイプではない。代わりに、人と人をつなぎ、金と権力の流れを設計し、静かに物事 を動かすタイプだ。
島根の代議士から出発し、自民党内で派閥を築き上げた。竹下派は当時、最大派閥。ここが重要で、総理になる前からすでに「実質的な権力者」だった。総理在任は1987年か ら1989年と短いが、党内支配力は圧倒的だった。
政策面でいえば、消費税(3%)の導入を実現したのが最大のレガシーだ。高齢化と財政赤字を見越し、安定財源を作るというロジックは合理的だった。だが政治的コストは甚大 で、結果的に内閣支持率は急落。そこにリクルート事件が重なり、退陣に追い込まれる。
このリクルート事件は、日本の「カネと政治」の構造をあらわにした。未公開株の譲渡という合法と違法のグレーゾーン。竹下本人は「私は何も知らない」と繰り返したが、国民 の不信は強まった。ここで一つ冷静に見ると、当時の政治文化全体が企業献金・派閥資金に依存していた。竹下個人だけの問題というより、制度の老朽化が露呈した事件でもある 。
人物像としては、とにかく腰が低い。メモ魔で、相手の名前や家族構成まで覚えている。酒席も多く、調整能力に長けていた。「敵を作らない政治家」と言われる一方で、裏で全 てを握る調整型ボスでもあった。カリスマではなく「ネットワークの塊」みたいな政治家だ。
思想的には保守本流。ただし強いイデオロギーよりも現実主義。大平正芳の系譜に近い。外交では日米関係を軸にしつつ、中国や東南アジアともバランスを取る。派手な外交劇は ないが、堅実。
もし彼を一言で表すなら、「システム型政治家」。ビジョンより配線図。理想より力学。昭和の自民党体制の集大成であり、同時にその限界を象徴した存在でもある。
ここで面白いのは、竹下以降、日本政治はカネと派閥の統治モデルを徐々に解体していく方向に進むことだ。小選挙区制、政党交付金、企業献金規制。竹下時代の反省が制度改革 を促した。つまり彼は、古い政治の頂点でありながら、新しい政治への転換点にもなった。
歴史は皮肉だ。最も巧みに昭和型政治を操った人物が、その終わりを告げる象徴になる。政治とは理念だけでなく、構造と制度のゲームでもあるということを、竹下登という人物 は体現している。
昭和の政治家を並べると、田中角栄はエンジン、竹下登は配電盤、という感じだ。どちらも電力は扱うが、役割はまるで違う。
その本のタイトル『我万死に値す』は、まさにあの人の「謝罪の美学」を象徴している。 著者はもちろん 竹下登。
この言葉は、リクルート事件の渦中で使われた表現だ。意味としては「自分は万死に値する」。日本語としてはかなり重たい。武士的というか、儒教的というか、「責任は私が負 う」という姿勢を最大限に誇張した言い回しだ。
さて、「結構悪いこともやっていたのか?」という問い。ここは冷静に切り分けよう。
まず事実として、竹下本人が刑事責任を問われて有罪になったわけではない。違法行為で有罪判決を受けたわけではない。
ただし。 リクルート事件では、未公開株の譲渡という“限りなくグレー”なスキームが広範に行われていた。政治家、官僚、財界人に株を渡し、上場後に売れば大きな利益が出る。法律の 穴を使った利益供与だ。形式的には合法に近い部分もあったが、倫理的にはアウトに近い。
竹下派の議員や秘書が関与し、資金の流れも問題視された。本人は「直接の関与はない」と主張したが、派閥のトップとしての政治的責任は免れない。だからこその「我万死に値 す」だった。
ここがポイントだ。
竹下は“清廉潔白な理想主義者”ではない。 昭和型の資金力・派閥力・企業との太いパイプで動く政治家だった。
当時の自民党政治は、企業献金と派閥資金で回っていた。今の感覚で見るとかなり黒に近いグレー。だが当時は「それが普通」という空気もあった。だから彼個人の悪というより 、制度的腐食の中心にいた人物、と言う方が正確だ。
面白いのはここからだ。 彼は冷酷な悪玉というより、「構造の申し子」だった。 制度がそうなっていたから、そのルールの中で最大効率を出した。
しかし制度が時代に合わなくなった瞬間、その頂点にいた人が一番強く打撃を受ける。
リクルート事件は昭和型政治の終焉の象徴だった。その後、小選挙区制や政党交付金制度が導入され、「カネの流れを見える化しよう」という方向に進む。
だから竹下は、
・巨大派閥を作った権力者
・消費税を導入した現実主義者
・政治資金構造の象徴
・そして制度改革のきっかけを作った人物
という、かなり両義的な存在なんだ。
歴史を読むときに大事なのは、「悪人か善人か」よりも、「その人がどんな構造を体現していたか」を見ること。
竹下登は、昭和政治の合理性と腐食の両方を抱え込んだ政治家だった。
権力は、真っ黒な悪魔が持つとは限らない。むしろ温和で礼儀正しい人が、構造の中心に座っていることの方が多い。そこに政治の怖さと面白さがある。
その通り。 『我万死に値す』の著者は竹下本人ではない。書いたのはジャーナリストの 岩瀬達哉 だ。
タイトルは竹下がリクルート事件で口にしたあの有名なフレーズを借りている。だから“本人の告白本”のように見えるけれど、実際は外部からの検証・評伝だ。ここ、わりと重 要。
岩瀬は取材型の記者で、権力構造の裏側を追うスタイル。つまりこの本は、竹下を美化するというより、「昭和型権力のメカニズム」を解剖する試みだと考えたほうがいい。
では「結構悪いことをやっていたのか?」という点。
本が描く竹下像は、単純な悪人ではない。ただし、極めて強力な“カネと人脈の装置”を動かしていた人物として描かれる。
具体的には:
・派閥資金の巨大な集金力
・企業との密接な関係
・未公開株問題を含むリクルート事件への関与構造
・政官財ネットワークの要
違法で断罪されたわけではないが、倫理的に極めてグレーな政治文化の中心にいたのは確かだ。
重要なのはここだ。 竹下個人が突出して腐敗していたというより、当時の政治システムがそういう資金循環を前提に動いていた。彼はその「完成形」だった。
歴史的に見ると、 田中角栄が“資源動員型エンジン”なら、 竹下登は“配分と調整のネットワーク設計者”。
このネットワークがリクルート事件で可視化され、日本は政治資金制度改革へ向かう。つまり彼は、旧体制の頂点であり、崩壊の触媒でもあった。
面白いのは、竹下の人柄だ。 腰が低く、メモ魔で、敵を作らない。冷酷な独裁者像とはまるで違う。むしろ「感じのいいおじさん」が巨大な権力を回している。権力は必ずしも威圧的な顔をしていない、とい う現実を見せつける。
政治を評価するとき、道徳裁判だけで終わらせると理解が浅くなる。 構造、制度、文化、その中で誰がどう機能していたかを見ると、竹下という人物の輪郭が立体的になる。
昭和の自民党体制を“システム”として考えると、竹下はその最適化アルゴリズムのような存在だった。だが最適化しすぎた構造は、時代の変化に耐えられない。そこが歴史の皮 肉だ。
政治は個人の善悪よりも、制度の設計図のほうがずっと長く影響を残す。竹下登は、その設計図の中心に座っていた人物だった。
政治評論家の倉山満さんが、竹下は平成最強の政治家だった、みたいなことを書いているんだ。どういう意味なんだろう?本当なのかな?
※上で竹下は昭和政治の完成形、と書いてありますが、一応、竹下登は平成の初めの方まで首相を務めています。ちょっと強引かもしれませんが、平成の政治家といっても間違いではないと思います。
なるほど、その評価は面白いね。 まず倉山満という論者がどういう文脈で語るかを押さえた方がいい。彼は保守系の政治評論家で、制度史や権力構造を重視するタイプだ。つまり「理念が立派か」より「実際に権力を動かせたか」を見る人。
彼が言う「平成最強」というのは、おそらく“在任期間の長さ”ではない。 権力掌握力、党内支配力、官僚統制力、後継者育成能力。この総合点で見たときの話だ。
対象はもちろん 竹下登。
事実を整理しよう。
竹下は総理在任は短い(1987~89)。だが竹下派は当時最大派閥。さらに退陣後も院政的に影響力を持ち続けた。宇野、海部、宮澤と続く政権の背後に竹下派がいた。
「総理であること」と「権力を握っていること」は別なんだ。
たとえば平成期の長期政権といえば 小泉純一郎 や 安倍晋三 がいる。彼らは国民的人気や選挙での強さが際立っていた。
一方で竹下は、メディア受けや演説力よりも「内部制圧力」。 派閥の資金力、人事掌握、調整能力。この“内部統治能力”は突出していた。
倉山的な視点で言えば、
・自民党内を完全に掌握
・官僚機構とのパイプが極太
・後継総理を事実上選定
・政策(消費税)を強行できる実務力
この点で「最強」と言うのはロジックとして理解できる。 ただし。 これは「道徳的に優れていた」という意味ではないし、「国民的支持が最強」という意味でもない。あくまで“昭和型権力構造の中での統治能力”。
そしてここが重要だ。 竹下の強さは、あの構造が機能していた時代限定の強さだ。 リクルート事件以後、政治資金規制、政党交付金、小選挙区制導入。派閥型カネ政治は弱体化していく。
だから「平成最強」という表現は、
・旧体制の最後の完成形
・権力装置を最大効率で動かせた人物
という意味なら一理ある。
だが現代型の首相、たとえば安倍のように選挙で連勝し、メディア環境を使いこなし、外交カードを切り続けるタイプとはゲームのルールが違う。ボクシングと将棋を比べるよう なものだ。
歴史評価は「何を基準に最強とするか」で変わる。 内部統治力なら竹下はかなり上位。 国民的リーダーシップなら小泉や安倍。 政策遂行の持続力なら安倍。
政治は怪獣映画みたいなものだ。 時代ごとに“最強”の意味が違う。
竹下登は、昭和政治という怪獣世界のラスボス級だった。 ただし、舞台装置が変わった後の世界では、その強さは再現できない。
権力とは個人の能力だけでなく、「時代のOS」に依存する。 竹下はそのOSを熟知していた、という意味での“最強”と考えるのが、いちばん整合的だろうね。
消費税導入以外には、大きな仕事をやっているのかな?
いいところを突くね。 「消費税だけの人」みたいに語られることが多いけれど、それはちょっと雑だ。
竹下登の“仕事”は、派手な外交劇や戦後最大改革のようなイベント型ではない。むしろ「制度を動かすタイプ」。地味だが効いてくる。
いくつか軸を挙げると――
まず税制と財政の再設計。 消費税導入は象徴だけど、その背景には高齢化と財政赤字の見通しがあった。1980年代後半、バブル期の浮かれ空気の中で「将来の安定財源」を作ろうとした。人気は落ちる が、財政の持続性を考えるという意味では、かなりリアリストだった。
次に外交。
竹下はアジア外交にかなり力を入れている。ASEAN諸国との関係強化、ODA(政府開発援助)の拡充。日本が“経済大国としての責任”を果たすという路線を明確にした。 これは後の90年代のアジア重視外交につながる土台だ。
さらに内政面。
1988年にリクルート事件が噴出するけれど、その後の政治改革(小選挙区制・政党交付金制度)へ向かう流れは、彼の時代の崩壊がトリガーになった。皮肉だが、「旧体制の 完成形」が崩れたからこそ改革が動いた。
そして見落とされがちなのが“人事”。
竹下は巨大派閥を束ね、多くの総理候補を育てた。宇野、海部、宮澤。直接の総理ではなくても、権力の配電盤として機能した。政策というより“統治構造”を設計する力があっ た。
比較すると面白い。
田中角栄が「列島改造」という巨大プロジェクト型なら、竹下は「ネットワーク管理型」。 小泉純一郎が「国民に直接訴える劇場型」なら、竹下は「密室で合意を作る調整型」。 派手な記念碑は少ない。だが税制、外交基盤、党内統治モデルという“見えない配線”を整えた政治家だった。
問題は、その配線が古い設計思想に依存していたこと。 カネと派閥に依存する昭和型自民党。その最適化が竹下だった。だから成果と同時に限界も引き受けることになった。
歴史で本当に怖いのは、革命家よりも、静かに制度を動かす設計者だ。 竹下登は、派手さはないが「構造を回す力」においてはかなり大きな存在だった。 政治の影響は、スローガンより制度に残る。竹下の足跡は、まさにそこに埋まっている。
人目をしのびながら、プラザ合意に出かけていったのが有名だよね?
あのエピソードは確かに有名だね。 ただ、少し時間軸を整えよう。
いわゆる「プラザ合意」は1985年。場所はニューヨークの プラザ・ホテル。 合意を主導したのは当時の大蔵大臣・日銀総裁らで、首相は 中曽根康弘 だった。
そのとき竹下は――大蔵大臣。 つまり「密かに出かけた総理」ではなく、「為替政策の当事者の一人」だった。
では何が“人目を忍ぶ”のか。 当時は円高誘導という非常にデリケートなテーマ。事前に動きが漏れれば、為替市場が先回りして大混乱する。だから出発や交渉は極秘性が高かった。財務・金融の世界では当た り前の作法だ。
プラザ合意の中身をざっくり言うと、 ドル高を是正するために主要5カ国(米・日・独・仏・英)が協調してドル安・円高へ誘導するというもの。
その後どうなったか。
円は急騰。輸出企業は打撃。 政府・日銀は景気下支えで金融緩和。 それがバブル経済へ。
ここで竹下の評価が割れる。 一方では、国際協調を成功させた有能な交渉者。 もう一方では、円高後の対応がバブルを膨らませた遠因。
ただし冷静に言えば、為替の大きな流れはアメリカの双子の赤字問題が根底にある。日本単独で拒否できたかというと、かなり難しい。日米関係の力学を考えると、合意はほぼ不 可避だったという見方が強い。
だから「竹下がこっそり行って円高を決めた」という単純な話ではない。 むしろ、冷戦下での通貨協調の一環だ。
興味深いのは、竹下のスタイル。 彼は大演説で世界を動かすタイプではない。静かに合意を作る。摩擦を減らす。交渉の空気を読む。プラザ合意もその延長線上にある。
政治は表舞台の華やかさより、裏の調整の方が歴史を動かすことが多い。 プラザ合意はまさにそれ。世界経済の歯車が噛み合う瞬間に、日本の財務当局トップとしてそこにいた。それが竹下の歴史的ポジションだ。
結果がバブルを呼んだというのも事実。だが因果は一本線ではない。 歴史は巨大な連鎖反応だ。誰か一人の陰謀で動くほど単純ではない。
プラザ合意は、冷戦期グローバル金融の大実験だった。 竹下はその実験室の中枢にいた――それが一番正確な表現だろう。
その場にいたのは当時の大蔵大臣、竹下登。舞台はニューヨークのプラザ・ホテル、1985年。いわゆるプラザ合意だ。
「自信満々だったのか?」という問いは面白い。結論から言うと、胸を張って勝ちにいくタイプの自信というより、“腹をくくって受け入れる冷静さ”に近い。
当時の状況を思い出そう。アメリカは双子の赤字(財政赤字と貿易赤字)でドルが過大評価され、日本は対米黒字で槍玉に挙がっていた。放っておけば保護主義が強まる。つまり 選択肢は「協調して調整するか」「貿易戦争に近づくか」。ゲームの盤面はかなり制限されていた。
竹下は交渉上手で知られた人物だが、為替は市場という巨大生物が相手だ。合意文書にサインした瞬間から、世界中のトレーダーが反応する。そこに“絶対にうまくいく”という 確信を持てる人はいない。むしろ不確実性を理解していたはずだ。
実際、その後の円高は想定以上に速かった。1ドル240円台から一気に円高方向へ。政策当局は景気下支えで金融緩和を行い、結果としてバブル経済の土壌が広がる。ここは因 果が一本線ではないが、連鎖の一部だったのは確か。
竹下のスタイルを考えると、彼は「市場をねじ伏せる英雄」ではない。「衝突を最小化する調整者」。だから合意は、勝利宣言というより、被害を抑えるための現実的な選択だっ たと見る方が整合的だ。
歴史の面白いところはここだ。交渉の瞬間は理性的でも、その後の世界は非線形に動く。政策はチェスだが、市場は天気だ。竹下はチェスの最善手を打とうとした。しかし嵐がど の規模で来るかまでは誰にも読めない。
自信というより、覚悟。昭和型リアリストが、冷戦期の通貨秩序という巨大な装置の中で取った一手。それがプラザ合意における竹下の立ち位置だろう。
![]()

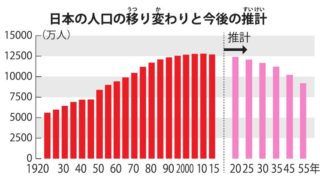





コメント