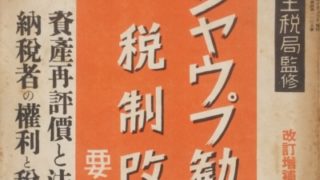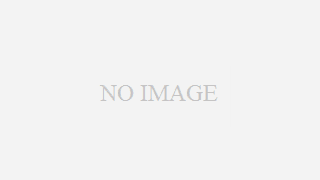親類縁者に共産党員がいる人を別にすれば、一般の人にとっての「共産党」というのは、どこか得体のしれない、宗教組織のようなイメージではないだろうか?
それでもある程度の年配の人にとっては「共産党ってこういうもんだよな」とイメージが付きやすいだろうが、若い人にはほとんど分からないのではないだろうか?
というのも共産党は歴史が古く、一番光彩を放っていた時代はもう数10年前だからである。共産党はとにかく歴史ある政党だ。だからとにかく歴史の話から見ていく。
ザ・日本共産党の歴史~まず戦前~
日本共産党は1922年に結成された。100周年を迎えているわけである。コミンテルン(共産主義インターナショナル)の日本支部として始まったのである。ロシア革命を成功させ、世界で初めての社会主義国家を樹立したという現実の重みゆえに、ソ連共産党が実質的に指導するコミンテルンの権威は圧倒的であった。マルクス・レーニン主義というイデオロギーも、民主集中制という組織原則も、ソ連共産党からの輸入品である。資金調達の面でも、日本共産党はコミンテルンに大きく依存した。
共産主義というのはよく知られているように、君主のような支配者が無く、労働者の集団によって治められている社会を作る、という立て付けである。ソ連共産党は実際に、ロシア皇帝のニコライ2世とその家族を虐殺し、ロシアの皇族を亡き者にしている。
それに先立つ1910年、日本の社会主義者は明治天皇の暗殺未遂事件を起こしていた。大逆事件である。幸徳秋水ら12名が処刑された。
その後1922年に結成された日本共産党も綱領に君主制の廃止(天皇制打倒)を掲げた。
しかし大逆事件の経緯もあり、共産主義が日本の国体を脅かす思想だと政府も早くから心得ており、1925年には治安維持法を制定して取り締まりの体制を整えていた。実際、各地で共産党員が検挙される事件が相次いだ。
1930年代に入ると特高警察による弾圧は激しさを増し、取り調べに拷問が伴うことが珍しくなくなった。拷問で命を落とした共産党員には小林多喜二もいる。さらに特高警察はスパイも用い、一斉検挙につなげた。一方で検察では思想検事が「転向」政策を取り転向を促すなど、日本共産党はあの手この手で追い詰められていった。共産党の内部でも、いつどうやって自分たちが検挙されるかの疑心暗鬼に陥っており、1933年には「スパイ査問事件」というものまで起こった。スパイと疑われた小畑達夫が、共産党内部の査問の最中に死亡したのである。この査問の責任者は後に日本共産党の中興の祖とまで言われる宮本顕治であった。
戦後
戦時中まで政府から徹底的に弾圧された共産党だったが、戦後、GHQが民主化方針の下、政治犯の釈放を打ち出すと、それまで反戦を訴えていた共産党の党員等が続々と釈放された。また、GHQ施政下で共産党が合法化されると、「共産党こそ反戦のヒーローだ」という風な見方が庶民の間で広まり、共産党員は一気に増大した。日本共産党の黄金時代はこの時期だという見方もあるようだ。
しかしそれも長くは続かない。共産党は党員拡大の勢いを駆って全国でゼネストを頻発させたが、これはさっそくGHQの不興を買った。また冷戦が激化の兆しを見せると、GHQはいよいよ共産党を警戒するようになった。
コミンフォルム批判
ここでさらに事件が起こる。コミンテルンの後を継ぐ国際的共産党組織コミンフォルムが、日本共産党の平和革命路線を批判した、いわゆる「コミンフォルム批判」である。平和革命路線は野坂参三が中心となって提唱していたものだった。日本共産党が本家の国際的共産党(もちろん中心部はモスクワ)から批判された格好になったのだ。これは日本共産党は「平和革命路線」等と生ぬるいことを言うのではなく、武装闘争を開始せよとの趣旨の批判だった。この背後には日本を朝鮮戦争の基地として使おうとするアメリカを、日本国内でかく乱させようとするスターリンの意思が働いていたと言われる。
ここで日本共産党は、野坂を擁護する所感派と、国際的共産党に順じようとする国際派に分裂することとなった。
日本共産党は事態の収拾を模索するも、分裂状態はしばらく解消されず、そのまま1951年綱領が採択された。それは武装闘争の必要性を暗示させるものだった。
そのまま50年代は、武装闘争の事件が繰り返される時代となる。皇居前広場にデモ隊が乱入して多数の死傷者が出た「血のメーデー事件」、中国共産党に倣って革命根拠地を作るための山村工作隊などが有名だ。
警戒心を強めた吉田内閣は52年に破壊活動防止法(破防法)を施行し、さらに法務局の外局として公安調査庁が設置された。
宮本顕治体制
1955年、六全協が開かれる。ここで1951年綱領が正しいとした上で、「極左冒険主義」は最大の誤りであったとの反省がなされた。またこの頃から、宮本顕治の主導体制が確立してゆく。
またこの頃、「敵の出方論」というかなり曖昧な玉虫色の革命論が唱えられた。革命の手段を自ら縛ることはしない、反革命勢力の出方次第で、革命戦略は変えられるというものであった。武装闘争を否定していないようにも見えるが、一応、党本部は基本的に、平和革命路線を進めていくような態度を取ったのである。
しかし同じ共産党勢力内に、平和革命路線は生ぬるいとして党本部に反発する勢力が続々と生まれた。主に若手の共産党員である。まず全学連が暴力革命を主張した。その後、同様、暴力革命を主張するグループとして、ブント、中核派、核マル派などが次々と誕生していく。コミンフォルム批判の時の所感派と国際派のような対立がここでも繰り返されているのである。
1961年の党大会で1961年綱領なるものが採択された。日本の現状を「高度に発達した資本主義国でありながら、アメリカ帝国主義になかば占領された事実上の従属国」と規定し、アメリカ帝国主義と日本の独占資本という「二つの敵」に対抗する「民族民主統一戦線」を作り上げることを主張するものだった。
1956年以降、中ソ対立が激化すると、日本共産党は中国寄りの立場をとるようになった。
またこの頃の日本共産党は原子力の軍事利用は悪、平和利用を善とする見方を示し、「いかなる国の核実験にも反対」とする社会党や総評と対立した。
中ソ対立が激化する中、キューバ危機でアメリカに妥協したソ連を中国は批判し、アメリカ帝国主義との対決を掲げる日本共産党も中国寄りの姿勢を示し、ソ連とは対立することになった。しかしその後、毛沢東が極端な反米反ソ統一戦線を強要しようとしたことに日本共産党は反発し、中国共産党とも対立することになってしまった。日本共産党は自主独立路線を進んでいくことになる。
1968年前後には学園紛争が盛り上がり、ここで新左翼が行動を急進化させた。
1974年、創価学会と共産党が従来の敵対関係の解消を狙い、前者が共産主義を敵視せず、後者も信教の自由を擁護し、相互理解に努め、ファシズムの攻撃に対しては相互に守り合うという趣旨の協定に署名した。その有効期間は10年で、署名の翌日には仲介者の作家・松本清張の自宅で池田大作会長と宮本委員長が会談して、確認した。創共協定である。しかしこれはお互いの幹部以外は事前に十分な了解を得ていない話であり、事態は協定どころか非難の応酬に反転してしまい、創共協定は空文化してしまう。
この時期、革新自治体の躍進という現象もあった。環境や福祉を軽視する自民党政権への反発が高まっていたことが背景になる。1967年からの東京都の美濃部都政、1950年からの京都府の蜷川虎三知事等の例がある。
1980年から社会党、公明党、民社党が連合政権構想で合意するという社公民路線が始まった。これに共産党は反発する。
1989年の天安門事件を日本共産党は激しく批判する立場を取った。
91年のソ連崩壊ももちろん国際的な大衝撃であったが、従来からソ連の新思考外交に批判的だった日本共産党は、あくまでも自主独立路線を貫くのみという恬淡たる態度を取った。
国際的にも孤立し、国内政界でも孤立したかに見えた日本共産党だったが、1994年の自社さ政権発足とともに、復調の兆しが見え始める。社会党は自衛隊を合憲と認め、日米安保条約を堅持する姿勢を示した。ここで共産党は社会党の政策的立場を一気に奪う戦略に出る。非武装中立を掲げ、9条を中心とした護憲の立場を示した。以後、共産党は「唯一の革新」を標榜し、社会党が自民党と連立を組んで従来の政策を放棄したことに失望した有権者の票を獲得することに成功していく。
1997年の党大会で宮本議長が引退し、不破・志位体制が確立する。